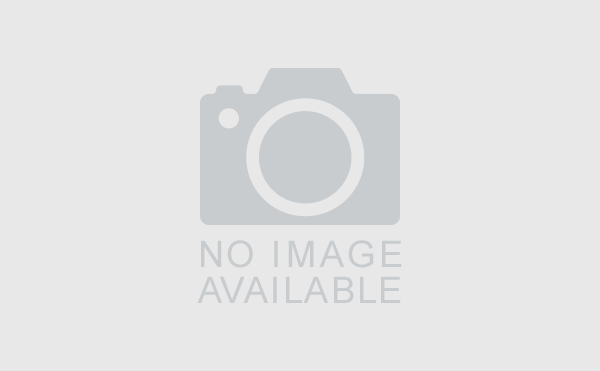高知県の防災レポート:南海トラフ地震と風水害への備え(2025年5月版)2025/5/21
防災最新速報!
こんにちは。2025年5月21日現在の情報に基づき、「防災 高知県」をテーマとした最新のレポートをお届けします。高知県にお住まいの方、ご関心をお持ちの皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
1. はじめに:豊かな自然と隣り合わせの災害リスク
エメラルドグリーンに輝く太平洋、緑豊かな四国山地、そして日本最後の清流といわれる四万十川。高知県は、その雄大で美しい自然環境から「日本の縮図」とも称され、多くの人々を魅了しています。しかし、この豊かな自然は、時として私たちに大きな試練をもたらします。
高知県は、近い将来の発生が危惧される「南海トラフ巨大地震」において、全国で最も大きな被害が想定される地域の一つです。また、台風の常襲地帯であり、毎年のように豪雨による浸水や土砂災害に見舞われるなど、複合的な災害リスクと常に隣り合わせの環境にあります。
だからこそ、高知県では「防災先進県」を目指し、県民一人ひとりの防災意識の向上と、地域社会全体の災害対応能力強化に向けた様々な取り組みが、行政、地域、そして個人レベルで進められています。このレポートでは、高知県が直面する災害リスクの最新情報と、それに対する多角的な防災・減災対策、そして私たち一人ひとりができる備えについて、できる限り網羅的にお伝えします。
2. 高知県の最新の災害リスク評価と想定
1) 南海トラフ巨大地震:待ったなしの脅威
最新の被害想定 国の中央防災会議が公表している南海トラフ巨大地震の被害想定では、高知県は最大クラスの地震(マグニチュード9.1)が発生した場合、県内で最大震度7の揺れに見舞われ、場所によっては30メートルを超える巨大な津波が数分で到達するとされています。
人的被害 最悪の場合、死者数は約4万2000人(うち津波による死者が大半を占める)、負傷者数は約3万6000人と想定されています。特に沿岸部では津波による壊滅的な被害が予測されます。
建物被害 全壊・焼失する建物は約10万7000棟に上ると推計されています。揺れによる倒壊に加え、津波による流失、火災による焼失が複合的に発生する可能性があります。
インフラ被害 道路の寸断、ライフライン(電気・ガス・水道・通信)の途絶、港湾施設の損壊など、社会経済活動に深刻な影響が出ると予測されています。
浸水想定 高知県の沿岸部の広範囲が津波により浸水すると想定されており、特に高知市、須崎市、土佐清水市、黒潮町などでは甚大な浸水被害が予測されています。最新のハザードマップでは、これらの浸水域が詳細に示されています。
発生確率 南海トラフ地震は、今後30年以内に70~80%という非常に高い確率で発生すると評価されており、まさに「いつ起きてもおかしくない」状況です。政府の地震調査委員会は、定期的に発生確率や長期評価を更新しており、常に最新情報を確認することが重要です。
「南海トラフ地震臨時情報」への対応 気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合に「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。この情報が発表された際の住民の行動や、行政の対応について、高知県や各市町村では具体的な計画を策定し、周知に努めています。特に「巨大地震注意」や「巨大地震警戒」が発表された場合の避難行動について、日頃から確認しておくことが求められます。
2) 台風・豪雨:激甚化・頻発化する風水害
近年の傾向 地球温暖化の影響も指摘される中、台風の大型化や、短時間に局地的な大雨をもたらす「線状降水帯」の発生頻度が増加しています。高知県は、四国山地の影響で雨量が多くなりやすい地理的特性を持ち、土砂災害や河川の氾濫、都市部での内水氾濫のリスクが高い地域です。
浸水想定区域・土砂災害警戒区域 県内の多くの河川で洪水浸水想定区域図が作成・公表されており、浸水深や浸水継続時間などが示されています。また、急峻な地形が多いことから、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)も広範囲に指定されています。これらの情報は、各市町村のハザードマップや県のウェブサイトで確認できます。
* 2018年の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)では、高知県内でも大きな被害が発生し、改めて風水害への備えの重要性が認識されました。
3. 高知県および県内市町村の防災・減災への取り組み
「防災先進県」を目指す高知県では、ハード・ソフト両面からの多層的な対策が進められています。
1) ハード対策:命を守るインフラ整備
津波対策
海岸堤防・護岸の強化・粘り強い化 津波の高さを完全に防ぐことは難しくても、浸水を遅らせ、避難時間を稼ぐための「減災」を目的とした堤防整備が進められています。
津波避難タワー・避難路の整備 津波からの避難が困難な地域を中心に、津波避灘タワーや高台への避難路(スロープ、階段等)の整備が進められています。2024年度末までに県内で約140基の津波避難タワー等が整備される見込みです。
建物の高床化・移転促進 危険区域内の住宅や事業所に対して、高床化や安全な場所への移転を支援する制度も設けられています。
耐震化の推進
住宅耐震化 県民の命を守る最も基本的な対策として、住宅の耐震化を強力に推進しています。無料耐震診断や耐震改修工事への補助制度があり、2025年度末までの耐震化率90%を目標としています(2023年度末時点で約87%と報告されています)。
公共施設の耐震化 学校、病院、庁舎など、災害時に拠点となる公共施設の耐震化はほぼ完了しています。
土砂災害対策 砂防堰堤の建設、急傾斜地の崩壊対策工事、治山事業などが計画的に実施されています。
インフラ強靭化 災害時にも機能する道路ネットワーク(緊急輸送道路)の確保、橋梁の耐震補強、ライフラインの耐震化や多重化などが進められています。
2) ソフト対策:知識と行動で備える
避難計画・ハザードマップ
* 各市町村では、最新の被害想定に基づいたハザードマップ(津波、洪水、土砂災害等)を作成し、全戸配布やウェブサイトでの公開を行っています。これらのマップには、避難場所、避難経路、危険箇所などが分かりやすく示されています。
* 住民説明会やワークショップを通じて、ハザードマップの正しい見方や活用方法の周知が図られています。
情報伝達体制の強化
防災行政無線 屋外スピーカーや戸別受信機の整備を進め、確実に情報を伝達する体制を構築。デジタル化も推進されています。
緊急速報メール(エリアメール) 携帯電話各社を通じて、避難情報や災害発生情報を迅速に配信。
高知県防災情報メール・防災アプリ「高知県防災アプリ」 登録者に対して、気象警報や避難情報、地震情報などを配信。アプリでは、ハザードマップの確認や避難所の開設状況なども把握できます。
SNSの活用 高知県や各市町村は、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSアカウントを活用し、リアルタイムな情報発信を行っています。
Lアラート(災害情報共有システム) テレビ、ラジオ、インターネットなど多様なメディアを通じて、統一された災害情報を発信。
多言語対応 外国人住民や観光客向けに、多言語での情報提供も進められています。
防災教育・訓練の充実
学校教育 児童生徒の発達段階に応じた体系的な防災教育を実施。避難訓練はもちろん、災害図上訓練(DIG)や防災マップ作りなども取り入れられています。
地域防災訓練 市町村や自主防災組織が主体となり、住民参加型の実践的な避難訓練や安否確認訓練、避難所運営訓練などを定期的に実施。
企業BCP(事業継続計画)策定支援 セミナー開催や専門家派遣を通じて、県内企業のBCP策定を支援し、災害時の事業継続能力向上を図っています。
備蓄体制の強化
公的備蓄 県や市町村では、食料、飲料水、毛布、簡易トイレ、医薬品などの備蓄品を分散して保管。7日分以上の備蓄を目指しています。
家庭備蓄の啓発 最低3日分、できれば1週間分の家庭備蓄を推奨。「ローリングストック法」(日常的に使う食料品を多めに買い置きし、消費した分を買い足す方法)の普及にも努めています。
共助・自助の促進
自主防災組織の育成・支援 地域住民による自主的な防災活動を推進するため、組織結成の支援、リーダー育成、活動費補助などを行っています。高知県の自主防災組織率は全国トップクラスです。
ボランティアセンターの設置・運営訓練 災害発生時のボランティア受け入れ体制を整備。
要配慮者支援 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人など、災害時に特に支援が必要な方々(要配慮者)の個別避難計画作成を推進。福祉避難所の確保や、地域での見守り・支援体制づくりを進めています。
3) DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用
AIを活用した災害予測 浸水予測や土砂災害発生危険度予測などにAI技術を導入し、より迅速で的確な避難判断につなげる研究開発が進んでいます。
ドローンによる被害状況把握 災害発生時、人が立ち入れない場所の被害状況をドローンで迅速に把握し、救助活動や復旧作業に活用。
デジタルハザードマップ ウェブ上で様々な災害リスク情報を重ねて表示できる「重ねるハザードマップ」の提供や、スマートフォンアプリとの連携。
避難所運営の効率化 避難者情報や物資管理をデジタル化し、避難所運営をスムーズにするシステムの導入が進んでいます。
4. 県民・企業ができること:自助と共助で命と暮らしを守る
行政の対策(公助)には限界があります。災害から命を守り、被害を最小限に抑えるためには、私たち一人ひとりの「自助」と、地域で助け合う「共助」の力が不可欠です。
1) 家庭での備え(自助)
住まいの安全確保
* 家具・家電の固定、ガラス飛散防止フィルムの貼付。
* 住宅の耐震診断を受け、必要であれば耐震改修を行う。
ハザードマップの確認 自宅や勤務先、学校周辺の災害リスク(浸水深、土砂災害の危険性など)を把握する。
避難場所・避難経路の確認 家族で複数の避難場所とそこに至る安全な経路を実際に歩いて確認しておく。「マイ・タイムライン」(一人ひとりの防災行動計画)の作成も有効です。
非常持ち出し袋の準備 避難時に最低限必要なもの(飲料水、食料、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、衛生用品など)をリュックサックなどにまとめておく。
備蓄の実践 最低3日分(できれば1週間分)の食料、飲料水、生活必需品を備蓄する(ローリングストック法を活用)。
家族との連絡方法の確認 災害発生時の安否確認方法(災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言板web171など)を事前に話し合っておく。
最新情報の入手習慣 日頃から気象情報や防災情報に関心を持ち、信頼できる情報源(自治体のウェブサイト、防災アプリ、気象庁など)から情報を得る習慣をつける。
2) 地域での協力(共助)
自主防災組織への参加・協力 地域の防災訓練や勉強会に積極的に参加し、顔の見える関係を築く。
近隣住民との声かけ・助け合い 特に高齢者や障害のある方など、避難に支援が必要な方への声かけや手助けを心がける。
避難所の運営協力 避難所が開設された場合、可能な範囲で運営に協力する。
3) 企業のBCP(事業継続計画)策定と実践
従業員の安全確保 避難計画の策定、安否確認システムの導入、防災備蓄品の整備。
事業継続のための対策 重要業務の特定、代替拠点の確保、サプライチェーンの確認、データのバックアップなど。
地域貢献 災害時に地域住民への支援(物資提供、施設開放など)ができる体制を検討する。
5. 近年の主な災害からの教訓(参考)
高知県では、2014年の台風第11号・第12号による豪雨や、2018年の平成30年7月豪雨などで、浸水被害や土砂災害が各地で発生しました。これらの災害からは、以下のような教訓が得られ、対策に活かされています。
早期避難の重要性 空振りや過剰避難を恐れず、「自分の命は自分で守る」意識で早めの避難行動をとることの徹底。
情報伝達の多重化と分かりやすさ 多様な手段で、誰にでも分かりやすい言葉で情報を伝えることの重要性。
「自分は大丈夫」という正常性バイアスの克服 ハザードマップで危険が示されていても、過信せずに避難することの啓発。
個別避難計画の必要性 要配慮者が安全に避難できるための具体的な計画と支援体制の構築。
6. 今後の課題と展望:よりレジリエントな高知を目指して
高知県の防災対策は着実に進展していますが、まだ多くの課題も残されています。
高齢化・過疎化と防災 担い手不足や要配慮者の増加が進む中山間地域などでの防災力維持・向上。
気候変動による災害の激甚化への対応 これまでの想定を超えるような災害への備え、適応策の推進。
複合災害・広域災害への備え 南海トラフ地震と台風の同時発生など、複合的な事態を想定した訓練や計画の見直し。広域避難や受援体制の強化。
DXの更なる活用と情報格差対策 防災分野でのデジタル技術活用を推進しつつ、デジタル機器に不慣れな層への配慮。
住民の防災意識の維持・向上 災害の風化を防ぎ、継続的に防災意識を高めるための工夫。若者世代へのアプローチ強化。
事前復興のまちづくり 被災後の迅速な復旧・復興を見据えた、災害に強いまちづくりの推進。
これらの課題に対し、高知県は「誰一人取り残さない防災」を基本理念に、県民、市町村、企業、関係機関と一体となって、よりしなやかで強い(レジリエントな)地域社会の構築を目指しています。
7. おわりに:防災は「自分ごと」、そして「みんなごと」
このレポートを通じて、高知県の最新の防災状況と、私たち一人ひとりが取り組むべきことについてご理解いただけたでしょうか。
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。しかし、日頃からの備えと正しい知識があれば、被害を最小限に食い止め、大切な命を守ることができます。
「自分だけは大丈夫」といった根拠のない安心感は捨て、災害を「自分ごと」として捉え、今日からできることから始めてみませんか。そして、ご家族や地域の方々と「みんなごと」として防災について語り合い、共に備えることが、高知県全体の防災力向上につながります。
このレポートが、皆様の防災意識を高め、具体的な行動を始めるきっかけとなることを心より願っております。引き続き、高知県やお住まいの市町村が発信する最新の防災情報にご注意いただき、安全・安心な毎日をお過ごしください。
標高・地盤認知の推奨
ステップ1
あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。
移転予定先の標高も調査しておきましょう!
※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)
ステップ2
あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。
移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!
ステップ3
地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!
海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。
縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?
防災認知ソース
PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)
移住・住宅・移住先の仕事
50平米550万円 車を買う値段で、家を買う。セレンディクス 3Dプリンター住宅
【Instant Products】「建てる」をもっと簡単に、「住む」をもっと自由に。
【ホームズ】空き家バンク | 地方移住・田舎暮らし向けの物件情報
ADDress | 月額9,800円から始める多拠点コミュニティサービス
【へーベルメゾン】HEBEL HAUSの賃貸住宅(旧へーベルROOMS)
地震に強い家 コンクリート住宅 パルコン | Palcon 大成建設ハウジング
災害に備える防災品
※広告